プロ野球が開幕しましたね。かつてほどの熱の入れようではないけれど、西武ライオンズの成績は一応気になります。ただ球場へ出かける気にはならない。あの応援団というのを何とかして欲しいわけです。
|
目次
1)認知症の父が教えてくれたもの
2)弱さが退けられる社会で
3)BREXIT:ある保守党議員の困惑
4)BREXIT:カミカゼ作戦の果てに
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
|
1)認知症の父が教えてくれたもの
|
 |
3月16日付のThe Observerにニッチ・ジェラードという作家:ジャーナリスト(女性)とのインタビュー記事が出ています。彼女が最近書いた"What Dementia Teaches Us About Love"(認知症が愛について教えてくれること)という名前の本について語っている。この本は認知症の父親に付き添ったニッチ自身の経験を基に書いたものなのですが、父親は10年間わたる認知症との付き合いの末、5年前に亡くなっています。ニッチは1958年生まれだから今年で61才になる。彼女はまた認知症のケアラーの福祉向上のためのキャンペーンにも取り組んでいる。 |

|
| Q:この本を書こうと思った動機は? |
書く必要がある・・・
Nicci:認知症については、優れた本がたくさん書かれているし、父親のプライベートな部分を公にするのは嫌だったけれど、認知症については「書く必要がある」(I
did need to write)と思った。認知症患者としての父親の人生を観察し、ケアラーたちのためのキャンペーンに取り組む中で、認知症とともに生きるとはどういうことなのかについて多くのことを考えたし、認知症という症状が私たちの「自己意識」(our
sense of self)や他人をどのように評価するかとか「弱い」(vulnerable)とはどういうことなのかについても・・・これらのことへの自分なりの思考法が激しく揺さぶられたということだ。
|
| Q:キャンペーンによって何を変革しようとしているのか? |
不必要な面会制限も
A:入院する前の父はかなりいい状態だった。認知症の進行も徐々に徐々にであったし、衰弱もごく優しいものだった。それがまるで爆発でもしたかのように急変したのです。急変の理由は、彼が5週間にわたって入院していた際に私たちとの面会が許されなかったということ、つまり彼が私たちを一番必要とした時期に面会が許されなかったということだった。ケアする人間にとっても、自分の一番愛する人間と一緒にいることが許されないということほど残酷なことはない。だいいち不必要な制限なのですよ。こればっかりは絶対に変えなければいけない(it
absolutely needed to be changed)ことだったと思うし、変えることは極めて簡単なことだったはずだ。
|

|
| Q:でも実際にはそれほど簡単なことではなかった、と? |
病院文化を変える
A:私たちの提案にはマイナス面など何もなかった。あれほどマイナス面が少ない提案も珍しいものだったと思う。なのに、国民健康制度(National Health Service: NHS)がバラバラ状態なのに官僚的であるが故に何もできなかった。つまりそれぞれの病院における文化そのものを変えなければということになってしまった。あちこち駆けずり回り、看護婦と話をして、誰もが納得してこの変革運動に加わってもらうように努力したり・・・いろいろと苦労はあったけれど、今では英国中のあらゆる熱心な病院が私たちの運動に賛同してくれていると思う。
|
| Q:認知症に直面する社会としての英国は良くなっていると思うか? |
考えまいとすると
A:良くなっていると思う。十分とは言えないまでも、世の中40~50年前に比べれば大きく変わった。私の父親の世代にとって、認知症は相変わらず「恥ずかしいもの」(stigma)だ。その話はしないし、場合によっては認知症であることを否定したり隠そうとしたりもした。そうすることの方が本人にとっても周りの者にとっても苦痛が増えるだけなのに、だ。しかし若い世代はそのことを語ろうとしているし、本を書こうともしている。テリー・プラチェット(作家 1948~2015)の場合、彼と話をするとき認知症が必ず話題に上ったものだ。それは会話の一部でもあったのだ。認知症を怖がる人もいるし、それなりに正しい部分はある。事実非常に怖ろしいのだから(it is very scary)。でも認知症は、そのことを考えないようにしようとしたときに余計怖いものになるのだ。It becomes more scary when you try not to think about it. |

|
| Q:認知症に罹っている人から学ぶべきものはあるか? |
人間であること
A:もちろんある。最初に言っておきたいのは、認知症に罹っているとはいえ、罹る以前と同じ人間であり、我々と同じ世界に住んでいるということだ。彼らなりの価値観のようなものを持っているのだ。私自身、何度も目にしてきたことだが、認知症に罹っている人が愚か者や物体のように扱われたりしている。彼らは脳の病に罹っているだけで、彼らなりに世の中に貢献できることはあるのだ。
さらに大きな観点からいうと、認知症が人間に突きつける課題は「人間であるとは何を意味するのか」(what it means to be human)を問うということなのだ。特に欧米の社会では独立・若さ・活力・目的意識・自給自足などということに大きな価値を求めようとする。しかし人間が若くなければ健康でも自立的でもなくなって他人の世話にすがらざるを得なくなったら、どうするのか?
|
| Q:この本を書くためにいろいろとリサーチが必要であったと思う。ストレスを感じたのでは? |
楽観的になった
A:ほぼ全く反対だった。父が死ぬ前も死んだ後も、あちらこちらと動き回ったし、悲劇的な感じがしたこともあった。この本を書くためにリサーチを行い、認知症の人間とも会い、それについて考えたり本を読んだりもした。その結果として、自分では以前よりもはるかに楽観的になったと感じている(I
felt immensely more optimistic by the end)。この本は単なる絶望物語ではなくて、愛と勇気と冒険の物語なのだから。It’s
a story of love and courage and adventure.
|

|
| Q:認知症について細かく調べたり見つめ直したりした結果、あなた自身の恐怖心が小さくなったと言えると思うか? |
自身の出口を求めて
A:答えはイエス。でも認知症の痛ましさが小さくなったとかいう意味ではない。ただそのことについて以前よりも考えることが多かったので恐怖心が小さくなったということだ。それは今まで自分が見つめまいとしてきた世界に光を当てたようなものだ。認知症について、自分自身の出口を見つけようと試みる気がしているということだろう。認知症が怖ろしいというよりも「宴会が終わる前に去りたい、宴会が終わって一人っきりに取り残されたくない」(wanting to leave the party before the party leaves me)ということだ。
|
| Q:つまり・・・認知症になるる前に自分の命を絶ちたい、と?You mean you would take your own life before dementia took hold? |
A:そういうことだが、そのように言ってしまうことには躊躇を感じる。なぜならそれ(自分で命を絶つこと)はとても難しいことであろうから。自殺というものはその能力がある間にするものだ。そんなときが来たなら、実際には、もう一度だけあの山に登ってから、もう一杯だけワインを飲んでから、もう一回だけ家族と食事をしてからなどと考えるようになるのだろう。
|
| Q:この本を書くことでお父さんの死と向き合うことの助けになったことはあるか? |
「癒しの手」を置く
A:ある。何が起こったのかを考え、それを受け入れ、そしてすべてに対してサヨナラを言う・・・そのようなことを自分自身に許したということだろう。自分が置かれた状態に「癒しの手」を置こうとするような感じだった。It
was like trying to lay a healing hand on it. それこそがこの本を通じて自分のやりたかったことなのだ。つまり混乱に満ちて滅茶苦茶で酷いものになるかもしれない病の上にそっと「癒しの手」を乗せるということだ。 |
|
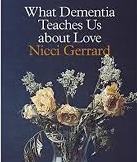 |
▼インタビューの中の最後の二つのQ & Aがこのインタビューのハイライトかもしれないですね。父親のような状態になる前、即ち何もかも分からなくなってしまう前に自分の命を絶ちたい・・・などと思うのはアタマの中だけの話で、実際にはそのようなことはできないだろう、と。認知症の父親に寄り添いながら、そのことについて本を書くということは、きっちり考えるということですよね?違います?そのことが認知症という病の上に「癒しの手」を乗せることになる・・・人間にできることは、そっと付き添うだけということかもしれない。
▼同じ3月16日付のThe Observerにニッチ・ジェラードが書いた本からの抜粋が掲載されていますが、それは次のところで別に紹介します。 |
|
back to top
|
|
2)弱さが退けられる社会で
|
 |
ニッチ・ジェラードが認知症の父親をケアする日々と彼女自身の認知症に寄せる思いを書いた"What Dementia Teaches Us
About Love"という本からの抜粋がThe Observerのサイト(3月16日)に掲載されています。タイトルは‘Dementia
is the plague of our time, the disease of the century’(認知症は現代の疫病であり、21世紀の病だ)となっている。「抜粋」と言ってもそれなりの長さで、ここですべてを紹介するのは無理なので、むささびなりに面白いと感じた部分のみをほんの数か所だけ紹介してみます。
|
 |
ニッチの父親は2014年に亡くなるのですが、その前の年にニッチの家族と一緒にスウェーデンへ旅行します。そのときの父親の様子を次のように書いています
- 幸せそうで寂しげで
年老いて、か弱くなった父は、それでも数メートルだけ湖を泳いだ。そのとき歌を口ずさみ始めたのだ。私が全く聞いたことがない歌だったし、あれからも聞いたことがない。父は湖をぐるぐる回りながら泳ぎ、そして歌っていた。とても満足気で、幸せそうにさえ見えた。でもそれはとてもとても寂しい景色でもあった。この世には誰もいない、いるのは自分(父)だけ。夕暮れの薄明りとあふれるような静けさの中で、そこにいるのは湖と木と月と星だけ・・・。
- 生命の不思議
自己の端は柔らかく、自己の境目は薄くて孔がたくさんあいているものだ。The edges of the self are soft; the boundaries of the self are thin and porous. あの瞬間、私は、父と世界が一つになっているということを信じることができた。世界が彼の中に流れ込んで行っており、彼は自分を空っぽにして世界の中に溶け込んでいる。彼の自己は、長年にわたる認知症のおかげでバラバラにされていたけれど、その優しい瞬間だけは、言葉も意識も恐怖もすべてを超えて、命の大きな奇跡が生み出す幾重にも重なったものの中に包み込まれ、生命というとてつもなく大きな不思議の中に安住していた。
|
| ▼「自己の端は柔らかく・・・」という部分の意味は分からないけれど、ほぼ10年に及ぶ認知症という病とそれに伴う医療行為のお陰で「父親自身」(self)というものがズタズタされてしまっていた。それが湖に身を浸し、星や樹木を眺めている中で生き生きとしているように見えた、ということなのでしょうね。ニッチは後日、あのスウェーデンの湖における父親の様子を「自己と世界の神秘的な融合状態」(mysterious
fusion of the self with the world)と呼んでいます。 |

1950年代、結婚したばかりのニッチの両親 |
|
ニッチは父親の認知症と付き合う中で「自分であるとはどういうことなのか、人間であるとは何なのか?」(what is it to be a self,
to be human)という問いかけを行います。人によっては認知症を「現代の疫病」(plague of our time)と呼んだりしているけれど、認知症は昔からあったのではないか、とニッチは考える。
- 弱さが退けられる社会で
認知症に罹っている人は、行方不明者(missing people)のようなものなのではないか。社会で忘れられ、存在さえ否定されている人びとだ。その社会においては独立・繁栄・若さ・成功のようなものが最大限に尊重され、弱さ(vulnerability)は退けられる。
ニッチが話をしたあるドクターは認知症について、極めて横柄な(profoundly disrespectful)病であると語っている。患者にとってもケアラーにとって実に手におえない存在であるということで、それは現代の保健・福祉制度にとっても「横柄」な存在である、と。要するに認知症はこれまでに人間が作ってきたあらゆる制度や枠組みにもフィットしない存在なのだということです。 |
| ▼「現代社会においては弱さが退けられる」というニッチの言葉を読んで、前回のむささびで紹介した、障害者施設における殺人事件の被告が言った「障害者に安楽死を」という言葉を思い出した。ニッチの文章では「弱さ」を"vulnerable"という言葉を使っている。"vulnerable"には「傷つきやすい」とか「影響を受けやすい」という意味がある。主に肉体的・物理的な「弱さ」を表す"weakness"とはニュアンスが違う。 |
 |
|
英国のアルツハイマー協会によると、認知症の社会的コストは英国だけでも年間260億ポンド、世界的には8180億ポンドともいわれている。これはガン、心臓麻痺、その他の心臓病の三つをあわせたものより大きい数字なのだそうです。ただニッチは、認知症がもたらす影響(impact)は数量化できない部分、「人間としてのコスト」(costs
in human terms)に目を向けようと言っている。即ち認知症者とその周辺の人びとが背負う「恥・戸惑い・恐怖・悲しみ・罪悪感・孤独感」(shame,
confusion, fear, sorrow, guilt, loneliness)などの負担です。
- 社会的価値観への疑問
そのことは、我々が暮らす社会そのものについての深刻な道義的な疑問を投げかける。自分たちがこだわっている価値観、さらには人生の意味そのものについての疑問の念ということだ。It provokes profound moral questions about the society in which we live, about the values we hold and about the meaning of life itself.
| ▼むささびは"meaning of life"という言葉に何気なく「人生の意味」という日本語を当てているけれど、"life"という言葉には「生命」という意味もあるし「生きていること」という意味もある。ニッチが言いたいのは、認知症を考えるということは正に"meaning of life"を考えるということ、というわけですよね。 |
|
| back to top |
3)BREXIT:ある保守党議員の困惑
|
 |
EUと自分が取り決めた離脱に関する「合意案」を可決してくれれば、自分は首相の座を降りる・・・とメイさんが明言して大騒ぎになったのが(日本時間の)木曜日の朝だった。金曜日にその合意案についての採決が行われ、土曜日の朝、ラジオのニュースを聴いていたらこれが344票対286票=58票差で否決された。つまりメイさんにしてみれば、3度目の提案も否決されてしまったということになる。昨日(土曜日)午後のBBCのサイトには "Theresa May ponders fourth bid to pass deal" という見出しの記事が出ていました。メイ首相が4度目の提案を考えているということですよね。つまりBREXITがこれからどうなるのか、まださっぱり分からない。
「分からない」と言ってみても始まらないし、普通のメディアと競って新しい情報を提供するなんてことはできっこないし・・・というわけで、一人の政治家の動きに絞って紹介してみたいと思います。その政治家というのは、つい最近までメイ内閣でビジネス担当大臣を務めていたリチャード・ハリントン(Richard Harrington)という人です。もちろん保守党の下院議員でロンドン郊外のワットフォード(Watford)という町が選挙区です。1957年生まれ、オックスフォード大学卒で、保守党との関りは1998年以来だから約20年ですが、下院議員になったのは2010年の選挙だから議員歴は8年です。
3月26日にメイ首相宛てに大臣としての辞表を提出したのですが、英国では大臣が辞任すると大体、辞表がメディアを通じて公表されますよね。そうすることが規則というわけではない(と思う)のですが、署名入りの辞表そのものが新聞やテレビのサイトに掲載されることが多い。ハリントン議員の辞表の中にまず書かれているのは次の文章です。
- ワットフォード選出の国会議員としての自分の義務および優先事項は常に自分の選挙区に関わっている。自分は常に地元および国の利益を考慮しながら考え、行動する責任を負っている。そして自分の判断は常にそのような観点からなされなければならないということだ。As the MP for Watford, my duty and my priority is to my constituency, I have a responsibility to think and act in the local and national interest, and I am tasked with exercising my judgement in that respect.
|
 |
この人の公式サイトを見ると、2016年の国民投票では「残留」に投票している。なぜ残留を望んだのか?ハリントンによると、どのような国際組織も常に改革を必要としており、EUも例外ではない。英国はEUに残留することによって「中から改革を続ける(to continue to work to reform it from within)ことが大切だと考えていた。彼自身は、EUが陥りがちな「行き過ぎた管理・統一」のような発想には反対であったのですが、EU加盟国であることによる経済上のメリットは何物にも代えられないし、英国はEUの中にあって影響力を発揮するべきだ、と思っていた。
2016年6月、ワットフォードにおける国民投票の結果は「離脱に賛成」が23,419票、「残留に賛成」が23,167票というわけで、「離脱」が勝ったとはいえ、票差はわずか252票差だった。投票をしなかった有権者が約2万人いたのだから、彼らが投票所に行っていたらどのような結果になったのか分かったものではないというような票差だった。
|
 |
それでも「離脱」が勝ったことは事実であり、有権者の判断は尊重されなければ・・・というのでハリントンがとった行動は強硬離脱だけは阻止するという性格のものだった。
- はっきりさせておきたいのは、自分はBREXITを実現する決意でいるし、国民投票の結果を実現する決意でいる。しかしだからと言って国民の職場や英国経済が犠牲になることがあってはならない。I want to be absolutely clear that I am determined to see Brexit through, and deliver on the results of the referendum, but this must not be at the expense of jobs and the economy.
|

メイさんを挟んで、強硬離脱派のリーダー、ジェイコブ・リーズモグ議員(左)とハリントン議員
|
つまりメイ内閣の閣僚としてハリントンが目指していたのは、メイさんと同じ「ソフト路線」であると同時に「強硬離脱だけはさせない」という考えも強かった。しかしメイさんを取り巻く議員の動向を見ていると、強硬派に押し切られて「合意なき離脱」という事態になりかねない。この際、閣僚を辞任する方が選挙区および国全体の意見と歩調を合わせることになると思うようになって
- 従って私は、強硬離脱だけは起こらないようにするために他の議員とともに行動することを目的に政府を辞することにした。I have therefore
decided that I resign from the government to do all I can to prevent this
from happening and will work with other concerned colleagues in these efforts.
辞表には書かれていないけれど、メディアとのインタビューでは、「自分自身はそれを支持するものではないが、国民投票のやり直し」という考えは「正当性を持っている」(legitimate)と言っている。 |
▼ハリントン議員は金曜日に行われたメイさんの合意案への投票では「賛成」票を投じている。実は金曜日の投票では、ハリントンが目の敵にしていたはずの強硬派の保守党議員もメイの提案に賛成票を投じている。これが下院で支持されればメイさんが辞任、それ以後のEUとの交渉で自分たちが主導権を握れる・・・というのが強硬派の意図だったはず。そうなると、ハリントンにしてみれば、メイさんを支持した結果、BREXITの行方を強硬派にゆだねる事態になる可能性もある。
▼ハリントンについていうと、要するに本音はBREXITには反対なのだけれど、2016年の有権者による投票結果を無視するわけにもいかない、できればもう一度国民投票をやって、残留ということになってほしいということです。でもそれを口にするわけにはいかないので「EUを離脱はするけれど関係は続ける」という態度になってしまう。メイさんも同じです。本当はINかOUTかしかないのに、真ん中があるかのように主張し、行動している、それが混乱の基本原因であると(むささびは)思っているわけです。
|
|
|
back to top |
4)BREXIT:カミカゼ作戦の果てに
|
 |
自分が提案するEUからの離脱協定案(Withdrawal Agreement)を下院が可決してくれれば首相の座を降りてもいい・・・と表明したメイさんですが、残念ながら今回もまた否決されてしまった。メイさんの「辞めてもいい」発言をThe
Economistは "kamikaze gesture" と呼んでおり、3月28日付の社説で
- 首相による退陣の約束は、英国が陥っているBREXITをめぐる混沌からの脱出には何の役にも立たない
The prime minister’s promise to resign does nothing to solve Britain’s Brexit mess
とこき下ろしています。
|
 |
結果的にはメイさんが約束したような形にはならず、首相を辞めることもなかったわけですが、それでも保守党内の強硬派議員の中にはメイさんの提案に賛成票を投じた議員もいたのだから「カミカゼ作戦」も全くの無駄であったわけではないのかもしれない。ただ、The Economistの社説がなぜ"kamikaze gesture"(やけくそ作戦)としてこれを否定するのか?社説を読むと確かに(むささびとしては)納得がいく。
まず三度も否決された「離脱協定案」は、あくまでも英国がEUから離脱するやり方についての協定であって、これが下院で可決され、英国とEUの間で合意されたとしても、その後に英国とEUがこれからどのように付き合って行くのかを決める交渉が始まるわけです。メイさんのカミカゼ作戦によると、その後半の部分は自分が辞めた後の首相がリーダーとして進めて行くことになる。ではどのような人物がメイさんの後任になる可能性が高いのか?
|
 |
英国で前回の選挙が行われたのは2017年で、(例外は認められるけれど)法律的には次なる選挙は2022年5月までは行われない。現段階におけるメイさんの後継者とは保守党党首のことであり、その人物がとりあえず首相を務めることになる。当たり前ですが、党首を選ぶのは、国民ではなくて保守党議員と保守党党員です。現在の保守党員の数は約12万人なのですが、The Economistに言わせると、普通の英国人に比べれば「より白人、より年寄り、より金持ち」(whiter, older and richer)の人間が多く、EUに対しては強硬離脱を支持する人間が多いのだそうです。この12万人によって選ばれたリーダーは、BREXITに対する現在の英国民の意識を反映していると言えるのか?新しいリーダーを選ぶ12万人の保守党員と2016年の国民投票で「離脱」に投票した1740万人、「残留」に入れた1610万人との間では意識の点で何の関係もない。 |
 |
何をやっても党内の支持は伸びず連立相手の北アイルランド民主連合党(DUP)からも反対されるのだから「カミカゼ」も仕方ないということなのでしょう。が、彼女が退陣したとしても、議会内における分裂は全く収まらない。彼女の離脱協定案については、党内の強硬派のみならずEU残留を主張する党内外の勢力からも反対されている。メイさんが退陣することで彼らが主張を変えるとは思えない。彼女の案に対しては保守党と労働党の両方から反対する議員が党を割って別の政治グループを作ったりもしている。メイが辞めようが残ろうが現在のような混乱と分裂が解消することはない。
|
 |
というわけで、The Economistが注目しているのは、BREXITをめぐるあり方を政府ではなくて議会が決めようとする最近の動きです。下院では3月27日(日本時間28日未明)に、議員によって提案されたBREXITのあり方に関する8つの選択肢についての「示唆的投票(Indicative
vote)」なるものが行われたのですが、8つとも否決されてしまったということがある。ただその中には大差で否決されたものと、票差が小さかったものがあった。例えば「合意なし離脱」は400対160で否決されたけれど、「もう一度国民投票」は賛成268:反対295で票差は27だったし、EU離脱後も関税同盟には残るという案は、賛成264:反対272で、否決されたと言ってもわずか8票差だった。 |
 |
BREXITをめぐる混沌から抜け出すために肝心なのは、議会および国全体において安定した多数派、それなりに合意形成ができた多数派(a stable, consenting majority)というものが存在することである、と。そのために必要なのは、議員の間における妥協の産物としての計画を作り出し、それを念のために国民投票にかけるというプロセスであるというわけで「メイさんはどうなるの?」という質問については
- このような発想に対して、メイ首相がこれを阻止しようとするのであれば、彼女には辞めてもらうしかないし、単に彼女が辞めるだけでは充分ではないかもしれない。If Mrs May were to dig in her heels against such a plan, her departure would be necessary. Even then it would not be sufficient.
というのがThe Economistの答えです。ちなみに先週8つの提案をすべて否決した「示唆的投票(Indicative vote)」は明日(月曜日)に再度行われることになっています。 |
| ▼むささびの友人(英国人)の中にはEUからの離脱を望む人間も結構いる。そのうちの一人に「殆ど50年も前に懇願してEU(当時はEEC)に加盟しておきながら、今更やめたいとは何事か」と言ってみたら、彼の言い分は「でもいまのEUは昔のEUではなくなった。クラブに加盟しても、それが自分の好みに合わなくなったら止めるのは当たり前だ」というものでした。それに対してむささびが「嫌になったから止めるというのはダメ。ほかの加盟国と一緒に改革する努力をすべきだ。EUを会員制クラブのように考えるのは間違っておる」と親切にも教えてあげたところ、返ってきた返事は「いやEUはクラブだ」というものでした。困ったものです。 |
|
back to top |
5) どうでも英和辞書
|
| A-Zの総合索引はこちら |
 |
notoriety: 評判・有名・悪名
"notoriety"をケンブリッジの辞書で引くと"the state of being famous for something bad"と説明されています。「悪いことで有名になっている状態」です。最近この言葉を使ったのがニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相です。3月15日にクライストチャーチのイスラム教のモスクを襲撃、50人を射殺したオーストラリア人の犯人について、事件直後の議会で次のように演説している。
- He sought many things from his act of terror, but one was notoriety - that is why you will never hear me mention his name. あの男はテロ行為を通じていろいろなことを成し遂げようとしました。その一つが自分が有名になることです。従って私は決して彼の名前を口にすることはいたしません。
なるほど、名無しの権兵衛(nameless)扱いするという対処もあるんですね。ここをクリックすると、首相がこの言葉を使った演説の動画が出ています。
むささびはむしろこの言葉の形容詞(notorious)の方が頻繁に聞いたことがある。"a notorious gambler"と言えば、悪い意味でのギャンブル好きとして知られているという意味だし、
- That newspaper is notorious for its sensationalism.
|
back to top |
6)むささびの鳴き声
|
▼とりあえず思いつくままに。あした(4月1日)、新しい年号が発表されるのですよね。数日前にラジオを聴いていたら、あるコメンテーターが「自分は年号をボイコットする」と言っていました。日本の年号は使いにくくて・・・という人はたくさんいるし、インターネット時代の現在はどうしても西暦の方が使いやすい、だから使わない・・・というのであればよくある意見であるし、むささびも同じです。ただこの人が言っているのは、使いやすい・使いにくい云々という問題ではなくて、国家による押し付けが嫌なのだということです。むささびとしては、これも非常に分かる。「平成」を発表したときの小渕恵三さんの顔と発表の雰囲気はよく憶えており、さして嫌な気持ちはしなかった。なのに何故、今は違うのか?あの人に何かを強制されること自体が我慢できない・・・と、この辺で止めとこ。
▼どうでもいいことですが、昭和元年は1926年、明治元年は1868年ですよね。前者は「解く風呂敷(1926)から昭和が出」、後者は「いやあロッパ(1868)くん、明治だよ」というわけです。平成元年って西暦では何になるの?分かりません。それから・・・あたいが生まれたのは昭和16年でございます。
▼「40~64歳という中高年の引きこもりが61万人に達し、若い世代よりも多い」というニュースを報道するNHKが「50代の引きこもり人間」として使った人物が「整えた髪でキレイなワイシャツ姿、さらに日焼けし腕時計をしながらMacBookを扱う人物」だったことで異論が噴出することになってしまったのだそうですね。異論風コメントの一つに「仲間がいると思って安心しかけたのにふざけんな」というのがありました。素晴らしいセンスです。この人がひきこもりとはとても思えない。だいいち「他人に顔を見せずに自分の部屋にいる」ことの何が悪いんですか?これ、内閣府が発表した資料に基づく報道なのですよね。「ひきこもり」を恰も「避けなければならない悪いこと」と決めつけることに新聞や放送が一役買っている。これも「記者クラブの弊害」です。
▼2020年度から小学校5、6年で英語が正式教科として教えられるのだそうです。3月27日付のYahoo!ニュース(時事通信)に、そのための教科書検定が行われたという記事が出ています。教科書会社7社が申請したとのことで「基礎的な英単語や日常会話などを、豊富なイラストを交えて教えるほか、聞く・話すを重視し、能動的な授業を進めるための工夫がなされている」のだそうであります。新学習指導要領なるものによると、日本の子どもたちは小学校卒業までに600~700の英単語を学ぶことになっているんだそうであります。ため息が出ません?
▼文部科学省のサイトの中に「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」というセクションがあります。それには「2014年度から逐次改革を推進する」と書いてあるところを見ると、この計画はすでに5年前から実施されているわけですよね。その中に「2020年(平成32年)の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、新たな英語教育が本格展開」できるようにするとも書いてある。日本人は英語が下手なんてこと何十年言われているのか?むささびが素朴な疑問として考えるのは、小学校5、6年から英語を教えれば日本人の英語力が向上するというのであれば、なぜ50年前からやらなかったのかということです。はっきり言うと、「日本人は英語が下手」ということ自体が本当ではないのではないか?
▼くだくだと失礼しました。 |
|
back to top |
←前の号 次の号→ |
 |
