| home |
backnumbers |
uk watch |
finland watch |
| むささびの鳴き声 |
美耶子の言い分 |
どうでも英和辞書 |
green alliance |
| 2009年8月16日 |
 |
| 8月15日も過ぎると夏もお終いという気分になりますね。関東地方は本日(8月16日)はカンカン照りですが、ほとんど夏らしい日はありませんでした。ところで、むささびジャーナルを開いたときに文字が異常に大きく見える人はいませんか?Microsoft Internet Explorerを使ってお読みになっている場合、画面の上のツールバーに「表示」というのがありますよね。それをクリックすると「文字のサイズ」というコーナーがあります。そこにカーソルを合わせてクリックすると、いろいろなサイズが出ていますので、その中の「小」をクリックしてもらうと、まともなサイズ(私が意図したサイズ)になります。 |
|
目次
1)保守党の公開予備選挙
2)NEWSWEEK「英国の衰退は避けられない」
3)マードックのニュースサイト有料化宣言
4)小沢一郎がThe Economistの読者に訴えたこと
5)どうでも英和辞書
6)むささびの鳴き声
|
| 1)保守党の公開予備選挙 |
 何度か紹介したのですが、遅くとも来年(2010年)6月までには英国の総選挙が行われます。最近の英国の政治を見ると、1979年から1997年までの18年間が保守党、1997年から現在までの12年間が労働党という具合に一つの党の政権が長くもつという傾向にあるけれど、今の段階での世論調査によると次なる選挙ではキャメロン党首率いる野党の保守党がかなり優勢とされている。 何度か紹介したのですが、遅くとも来年(2010年)6月までには英国の総選挙が行われます。最近の英国の政治を見ると、1979年から1997年までの18年間が保守党、1997年から現在までの12年間が労働党という具合に一つの党の政権が長くもつという傾向にあるけれど、今の段階での世論調査によると次なる選挙ではキャメロン党首率いる野党の保守党がかなり優勢とされている。
この選挙に関連して、保守党が候補者選びのために「公開予備選挙」(open primary)という方法を採用しているのですが、8月4日付のGuardianにこの方法による候補者選びの実例が報道されていました。
保守党の「公開予備選挙」は、ある選挙区において保守党候補者を何人かリストアップして選挙するのですが、これまでのように党員だけが選ぶのではなく、地元の選挙民にも投票権を与えるという方法をとっている点がユニークであるわけです。
記事が報告しているのは、Devonという地方にあるTotnesという選挙区で、公開予備選挙の結果、Sarah Wollastonという女医さんが選ばれた。Sarah Wollastonは女医歴23年の47才で3人の子供の母。公開予備選挙では「英国がヨーロッパという超大国(EUのこと)に呑み込まれることに断固反対する(fiercely opposed to Britain becoming swallowed up by a European superstate)」ことを訴えたのだそうです。
保守党では、これまでにもいろいろな選挙区での集会を開き、そこで党員・非党員による公開予備選を行ってきたのですが、Totnesの場合は地元の有権者6万9000人全員に投票用紙を配布して参加を呼びかけるというやり方をとった。「英国史上、最初の完全公開予備選挙(Britain's first full "open primary")というわけです。
選挙では当選した女医さんを含めて3人がリストアップされたのですが、投票率は24%で得票数は、女医さんが7914票、保守系地方議員が5495票、地元の市長が3088票だった。保守党のEric
Pickles幹事長は投票率が15%以上(投票者数1万人)であれば大成功と思っていたのだから、今回の結果には「民主主義の大いなる成功だ(a great success for democracy)」とコメントしています。ただこのようなやり方を全国的に実施するのかについては、コスト面も考える必要があるとしています。Totnesのopen primaryは4万ポンド(約640万円)かかったそうです。
予備選を公開方式にすることの良し悪しについては異論もある。「党員以外の人に参加を許すと、他党の人間が、総選挙でイチバン弱そうな候補者に投票するというサボタージュをやるのでは?」という声もある。その点について、公開予備選支持派の保守党議員は「予備選の候補者をリストアップするのは党なのだから、総選挙で勝てそうにない候補者を立てるはずがない」と言っています。実は外務大臣のDavid Milibandのように労働党の幹部の間でも公開予備選を希望する声があるのだそうです。
保守党のPickles幹事長は、今回の予備選の成功が明らかにしたのは「国民を信用すれば、みんな民主主義を受け入れられるということだ」(if you trust the people they embrace democracy)とコメントしています。
▼最近の経費スキャンダルにみるように英国の政治は明らかに変革期に入っています。英国は(日本においては)議会制民主主義のお手本のように言われてきたけれど、当の英国人たちの間ではそれほどでもないという不満が蓄積されているのかもしれないですね。
▼もう一つ興味深いのは、Totnes選挙区で選ばれた女医さんの政治思想とキャメロン率いる保守党全体の方針とが本当に一致するのかということです。女医さんの反EU的コメントからすると、彼女はサッチャーびいきなのではないかと(私などは)想像するわけです。つまり必ずしもキャメロンの考え方とは合わないかもしれない。次なる総選挙では保守党がかなり議席を増やすと予想されているのですが、中にはキャメロン路線に同調しない議員も出てくる。それをどのようにまとめていくのか?キャメロンさんの手腕が試される。
▼英国保守党のopen primaryを日本で実施するとどういうことになるんでしょうか?麻生さんが自民党の総裁に就任した際の総裁選挙では、麻生・小池・石原・石破・与謝野の5人の候補者が全国で集会を開いたり、日本記者クラブで「討論会」をやったり、テレビ局まわりをしたり・・・ということでお祭り騒ぎはやったけれど、民主主義とは何の関係もない。自民党の広報活動にすぎなかった。 |
|
| 2)NEWSWEEK「英国の衰退は避けられない」 |
8月17日付の NEWSWEEKが英国、英国人にとっては意地悪ともいえる記事を掲載しています。題して「英国の偉大さは忘れよう( Forget the Great In Britain)、つまり Great Britainの Greatの部分は忘れてしまっていいという言葉遊び(だと思います)。イントロは
| 英国の衰退は不可避であった。しかし経済危機によって、最後の「帝国のふり」は誰もが考える以上に早くしぼんでいくであろう。Its fall was inevitable, but the economic crisis will shrink the last pretenses
of empire faster than anyone expected. |
となっています。筆者(Stryker McGuire)は10数年にわたってNEWSWEEKのロンドン支局長をやっている人なのですが、本文の出だしも英国人の気分を害すること間違いなしです。
| 大英帝国を失った後でさえも、数十年にわたって英国はポケット超大国のような顔をして世界中を闊歩していたのだ。Even in the decades after it lost its empire, Britain strode the world
like a pocket superpower. |
「ポケット超大国」という言い方はちょっとひどいけれど、英国は経済力と文化的な影響力、核兵器の所有、それから「アメリカとの特別な関係」(extraordinary relationship with America)という要素のお陰で、この小さな島国(this small island nation)は、自分の階級以上のパンチを繰り出すことができた(to punch well above its weight class)と。
▼つまり、実はフライ級なのにヘビー級のようなボクシングをしていたというわけですね。
▼その昔(1960年代の初め)アメリカの国務長官だったDean Achesonという人が、Great Britain has lost an Empire and has not yet found a role(英国は帝国を失ったのに自分たちの役割を見つけ出していない)と公の場で発言して、当時の英国人の怒りを買ったことがあります。アメリカ人のいうことを気にしすぎるんだよね。Stryker McGuireのこの記事もかなり一方的で、相手(英国)に対する理解(empathy)に欠けていると思います。 |
が、それも昨年来の金融危機で事態が変わってしまい、英国は世界において自らが果たせる役割について考え直す必要に迫られている。つまり「小さな英国」(Little Britain)あるいは「これまでよりは小さい英国」(a lesser Britain)としての役割ということである、というわけです。理由はいろいろあるけれど、基本的には経済力の衰えと政府の借金の増大です。
IMFの見通しによると、英国の国の借金が今後5年間でGDPと同じになり、経済・社会研究所(National Institute of Economic
and Social Research)は、国民一人当たりの所得が2008年の水準にもどるまでに6年かかるといっている。The country’s public debt is soaring, possibly doubling to a record 100
per cent of GDP over the next five years, according to the International
Monetary Fund. The National Institute of Economic and Social Research forecasts
that it will take six years for per capita income to reach early 2008 levels
again.
失業給付を受ける英国人の数が、1999年には130万人であったのが、いまでは200万人を超え、間もなく300万を超えようとしている。The number of Britons claiming unemployment benefits has jumped from 1.3 million (4.6 per cent of the workforce) in 1999 to more than two million and is on track to top three million. |
が、何と言っても大きいのは国防予算の削減です。McGuireによると、歴史的に見ても、英国程度の規模で、国際舞台において英国ほど不釣り合いに大きな役割(a disproportionately large role on the world stage)を世界で演じている国はない。冷戦時代のサッチャーは、ソ連を屈伏させた指導者はレーガンと自分だと思っていたし、ブレア時代には、アメリカとともにコゾボ、アフガニスタン、イラクの3つの戦争を戦ったけれど、これからは戦争のためにこれまでのように税金を使うことは許されなくなる。Royal United Services Instituteというthink-tankによると、これからの6年間で英国の国防予算は11%削減されるとされている。
国防予算が減ると国際舞台におけるハードパワーとしての地位も落ちる。英国内の意識も変わってきている。Tridentと呼ばれる核ミサイルシステムを新しいものにするための費用(200億ポンド)をかけることに賛成の国民は半分を切っており、54%が核武装そのものを廃棄するべきだと言っている。
ハードパワーがダメなら「外交」のようなソフトパワーはどうか?実はこれも難しい。外務省の予算がカットされていて、2004年には300あった在外公館のうち19が閉鎖され、外務省のスタッフ数も6000人から4000人に減らされているのだそうです。また外務省に割り当てられる予算も今年(2009年度)は20億ポンドですが、来年度にはこれが16億ポンドにまで減らされると見られている(widely expected)。
| いまから11年前(1998年)、政権についてから1年後のブレア氏はアイルランドのダブリンにおいて「ポスト帝国の沈滞から抜け出す英国」を語ったものだ。「新しい労働党」「新たなる夜明け」「新しい英国」といったフレーズが大いに語られていた。ブレア氏が去ってから2年目のいま、ブラウン氏は、灰色で、とっくに賞味期限が過ぎたという印象を与えている。ブレア政権初期のころにロンドンがクールな町とされたCool Britanniaの文化的盛り上がりはとっくに消えてしまったのだ。Eleven years ago, the year after Mr Blair swept to victory, he spoke in Dublin of a Britain that was “emerging from its post-empire malaise”. Phrases such as “new Labour” and “new dawn” and “new Britain” were not yet curdling on the tongue. Today, Mr Blair is two years out of office and Mr Brown suffers from a grey, been-there-too-long aura. Long gone is the cultural ferment of Cool Britannia that made London the capital of cool in the early Blair years. |
NEWSWEEKによると、ブレア政権誕生のころの英国はかつてないほどの好景気で、移民が増えたお陰で文化的にも豊かになり、新しい起業家精神が古い産業地帯に新しい息吹を吹き込んでいた。つまり、あの頃の盛り上がりは「ホンモノ」であった。なのに・・・
| それは霧消してしまった。次なる首相にとっての大いなる試練は、大国の間における自らの位置を新たに定義しなおすことだけでなく、過去において英国を支配したような精神を再度取り戻すことにあるのだ。Today that has evaporated. The great test of the next prime minister will be not only to redefine Britain’s place among great nations but also to renew the kind of spirit that has ruled Britannia in the past. |
というのがStryker McGuireのエッセイの結びです。
▼私の記憶によるならば、Cool Britanniaとか言って初期のブレア政権を大いに盛り上げたのは NEWSWEEKとかTimeのようなアメリカの雑誌であって、英国の新聞・テレビや雑誌ではなかった。アメリカ人にCool!と言われて英国人も嬉しくなって、メディアも含めてみんな我を忘れてはしゃいでしまった。政府のプロパガンダも「文化的多様性」(cultural diversity)とか「創造性」(creativity)とか「若い英国」(young Britain)を押し出すものになり、「歴史と伝統」はタブー言葉になってしまった。
▼いまの英国は「文化的多様性」の源になった(とNEWSWEEKが言っている)移民に対する不満が右翼政党の台頭という形で表れているし、ビジネス面での「創造性」の象徴でもあった金融業界がアウトになってしまった。いろいろな面で転換期を迎えているという意味では、NEWSWEEKの言うことを認めるけれど、「昔の精神を取り戻せ」などと言われると、私自身、英国人ではないのに「あんたらアメリカ人には言われたくない」と言ってみたくもなる。 |
|
| 3)マードックのニュースサイト有料化宣言 |
TBSラジオのアクセスという番組を聴いていたら『メディア王・マードック が、新聞のネットを全て有料にする方針を発表。ネット版の有料化は、新聞にとって良いことだと思いますか?』というテーマで視聴者参加のディスカッションをやっていました。 が、新聞のネットを全て有料にする方針を発表。ネット版の有料化は、新聞にとって良いことだと思いますか?』というテーマで視聴者参加のディスカッションをやっていました。
メディアの世界で暮らしていない人にとって、ルパート・マードックがどういう人なのか馴染みがないかもしれないけれど、オーストラリア人で、英国ではThe Times、The Sunのような新聞、BSkyBという衛星テレビの経営者として知られています。アメリカではテレビのFox Newsとかビジネス紙のWall Street Journalなどを傘下に収めている人物です。
そのマードックが最近、自社経営のテレビや新聞のインターネット版をすべて有料化すると語って話題になっています。
| 上質のジャーナリズムは安くはない。コンテンツをただで手放すということは、優れたレポーティングを生む能力を犠牲にしているのと同じこと。Quality journalism is not cheap, and an industry that gives away its content
is simply cannibalising its ability to produce good reporting. |
と言っているのでありますが、要するに新聞、テレビでは広告収入が落ち込んでいるし、ビジネスとしての将来性はない。かといってネットの世界でも広告収入はそれほど伸びないというわけで、読者からお金をとろうということになっているわけです。現在の不景気が始まる前の2007年当時、マードックさんは、サイトの閲覧を無料にすれば読者数が増え、それが広告収入の増加につながると考えていたけれど、不景気のお陰で広告が伸びず、会社としても34億ドルもの損失を出すような状態になっている。仕方ないので読者からお金をとろう、ということになった。
メディア王の発言だから、注目を集めてはいるのですが、Financial Timesのサイトなどを見ていると「ライバル企業は懐疑的(Rivals sceptical of Murdoch’s charging plan)」というわけで、マードックの言うように「わが社が有料化に成功すれば他社も追随する」(I believe that if we are successful, we will be followed by other media)というほど確かなことではないようです。
例えば英国の大手新聞社、Trinity MirrorのSly Bailey社長は
| ユニークで価値が高く、差別化も図られているコンテンツについては、すでに有料化されている部分もある。一般的ニュースについては、BBCやGoogle Newsのような無料サイトが存在し続けるかぎり有料化することは不可能だ。While a paid online model already exists for unique, high value and well-differentiated content I doubt that it is possible for publishers to charge for general news content when the same content is given away for free by the BBC, Google News and others. |
と言って「問題は消費者が何に対してお金を払う気があるのかということであって、マードックの期待・希望とは関係がない」と指摘しています。
もちろんマードックの考えに賛同する関係者もいる。英国の新聞業界の専門紙、The Press GazetteのDominic Ponsford 編集長は、マードックが「優れたニュース報道の質はお金で価値を認められるべき(quality news should be valued and paid for)」と主張したことについて触れて「英国ジャーナリズムの救世主となる可能性もある」(Murdoch could prove to be the saviour of British journalism)とまで言っています。
英国では新聞の値段があがっていて、現在のところthe Independentが1ポンド、Financial Timesが2ポンド、The Guardian、Telegraph、Timesがそれぞれ90ペンスとなっているのですが、いずれも経営は厳しいのだそうです。
英国におけるニュースのサイトといえば何と言っても公共放送のBBCの無料サイトが圧倒的であるわけですが、Press Gazetteの編集長は、「マードックがBBCの独占状態について保守党関係者と会話を持ったことに賭けてもいい」(I’d wager that Murdoch has already had conversations with the Conservatives
to ensure that happens)と言っています。つまり政治力を行使して、BBCの独占状態を取り崩そうとしているということです。
▼優れたジャーナリズムを維持するにはお金がかかっているのだから、読者もそれなりのお金を払うべきだ・・・というマードックの主張は間違っていないとは思うけれど、結局のところ全部のメディア企業が足並みをそろえて有料化に踏み切らない限り現実には成り立たないわけですね。同じような情報を有料で提供するところとタダで提供するところがあるのなら、誰だって後者を選ぶのですから。
▼マードックは「わが社が有料化に成功すれば他社も追随する」と言っているけれど希望的観測にすぎない。そこで、他社が追随しなかったらどうするのかというと、この人の場合は政治力に頼ろうとする。サッチャーを支援し、ブレアを支援することでメディア王として君臨してきたという前歴がある。 |
で、最初に紹介したTBSラジオのアクセスですが、「ネット版の有料化は、新聞にとって良いことだと思いますか?」という問いかけに対して、「良いことだ」が87人、「よくないこと」が47人、「どちらとも言えない」が80人という結果でありました。つまり、どちらかというと「有料化は悪いことではない」という意見が多いということです。
▼TBSラジオのディスカッションの司会をしていたジャーナリストは「情報はタダ」という日本人の感覚が間違っているとして、ウェブサイトの有料化は正しいというニュアンスの話をしていました。それにしても有料化は「新聞にとっていいことか?」という質問をラジオの視聴者に向けるというのも妙な話ですね。視聴者(消費者)からすれば、なるべく優れた情報をなるべく安く(できればタダで)手に入れたいに決まっている。むしろ「社会にとっていいことか?」と聞くべきですね。そうすれば自分の問題として考えられるのだから。
▼で、これを自分の問題として考えた場合、「情報」とか「ニュース」とか「コメンタリー」などは、大根とかクルマとかパソコンのような「商品」と同じように考えるべきなのか?ということがあります。ニュースも商品なのだから、それを提供してお金をもらうのは当たり前だと(私は)思います。ダメなニュースならお金は払ってもらえないというのも当たり前ですね。それと「商品」というからには選択肢がたくさん欲しい。いろいろな新聞社がいろいろなサイトを提供するということです。
▼以前、日本の主要新聞3紙が共同のポータルサイトを作ったことがあったと記憶しているけれど、あれ、どうなっているのでしょうか?大きな新聞が3つもまとまるということ自体、消費者に対してアンフェアだと思うけれど、それ以前の問題として「まとまる」という発想そのものからして、「ダメだ、こりゃ」というところですね。 |
|
| 4)小沢一郎がThe Economistの読者に訴えたこと |
前回のむささびジャーナルで、民主党の小沢さんがかつてThe Economistに投稿した記事を読んだことがあるけれど、その号をなくしてしまったと後悔の念をお知らせしたところ「これですか?」と、その記事を送ってくれた人がおりました。どうも有難うございます。いまから13年前の1996年3月9日付の雑誌に掲載されたもので、この記事を投稿したときの小沢さんは新進党(New Frontier Party)の党首だった。エッセイのタイトルはThe Third Openingで、イントロは次のようになっています。
| Ichiro Ozawa believes that Japan, for the third time in little over a century, needs radical reform. In this article, he explains why he finds the prospect exhilarating. |
| 小沢一郎氏は日本は100年少しの間で3度目のラディカルな改革を必要としていると考えている。この記事では、彼がなぜ改革の展望が胸を躍らせるようなものなのかを説明している。 |
エッセイの本文は一人称で書かれています。小沢さんによると、第一の開国が幕末から明治維新、第二のそれが第二次世界大戦の終了時、そしていま(1996年)、日本は「第三の開国」(Third Opening)を必要としているというわけです。それは欧米から求められている市場の開放であり、国際社会において経済力にふさわしい役割を果たすということなのですが、日本自身の課題として「家族的で村落的な社会」(cosy village nature of Japanese society)という性格を乗り越える必要があると主張しています。
エッセイは非常に長いものだし、小沢さんの日本改造論はこれまでにもメディアによって語られているので、ここで要約してもあまり意味がない。そこでこのエッセイの中でも小沢さんがイチバン伝えたかった部分なのではないかと、私が勝手に想像する個所のみを紹介してみます。
まず規制緩和について「日本は1000年以上にわたって規制社会(regulated society)であったうえに、国土は小さくて人間だけが沢山おり、しかも天然資源がほとんどないという社会なのだ」として、そのような社会では、みんなが少しのものを分け合う「欠乏の経済」(economy of scarcity)が支配するのであって、規制はやむを得ない(there have to be regulations)と言っています。
そして「現代においては公平(fairness)や平等(equality)が、個人の自由(individual freedom)よりも優先されている」と言ってから次のように主張しています。
| We are a society without vast gaps between rich and poor, management and workers. We would like to keep it so, but not at the cost of stifling personal freedom and individual initiative. |
| 日本は貧富の差がそれほどでなく、経営者と労働者という分け隔ても大きくはない社会であり、我々(新進党)はそのような日本を堅持したいと考えている。しかし、だからといって個人の自由やそれぞれの自発性を犠牲にしてもいいというのではない。 |
この部分がまず面白いと思うわけです。「貧富の差のない公平な社会」を維持することに重点を置くのであればpersonal freedom(個人の自由)だのindividual initiative(それぞれの自発性)の方は少々犠牲になっても仕方ない・・・という方が理屈としては合っているのに、小沢さんは後者を犠牲にした「公平な社会」は意味がないと言っているように私には思える。どちらかというと、公平や平等よりも自由に重きを置いている(ように見える)。
次に「規制社会」についてさらに面白いことを言っています。長くなるけれど、まあお付き合いを。
| I know that most Japanese still feel uncomfortable and disoriented by the prospect of living in a society with few regulations and where each person will have to be more self-reliant and take greater responsibility for his or her own actions. |
| 殆どの日本人は、規制のない社会、すなわちそれぞれが自立し、自らの行動に対してより大きな責任を持つことが要求されるような社会で暮らすということに居心地の悪さと場違いさを感じるであろう、ということが私には分かっている。 |
と言ったうえで「しかし21世紀に突入する日本にとっては、これしか生き延びる術はないのだ(Nevertheless, there is no other way for Japan to move into the 21st century and survive)」と結論づけています。つまり規制の緩和と個人の自由や自発性が尊重される社会を目指すと言っているわけです。
最後に、規制が緩和され、個人の自由が優先される社会における政治のあり方について次のように主張しています。
| We have to move from decisions by consensus, so called, into the essence
of democracy, decision-making by the majority, with the minority accepting
those decisions in the belief that today's minority will become tomorrow's
majority. |
| 日本はいわゆる「コンセンサスによって物事を決める」というやり方から本質的に民主主義的なやり方に進まなければならない。それは「多数決」というやり方である。少数派は多数決による決定を受け入れると同時に、今日の少数も明日の多数になるということを信じるということである。 |
つまり小選挙区制による選挙と二大政党制の実現ということですね。自民党流の「話し合い」によるコンセンサス政治との決別宣言です。
▼以上は小沢さんの投稿原稿のほんの一部です。いうまでもなく日本語は私が勝手に翻訳しただけのものです。私の日本語がどうなっているということよりも、小沢さんという人のアタマの中がどのような英語でThe Economistという雑誌の読者に伝わったのかということをお知らせするのが私の目的です。
▼このエッセイを読むと、ひょっとしてこういうのを「マニフェスト」というのではないかと思ったりします。具体的な政策とか有権者との「約束」のような身近なものではなく、理念とか理想を語るということです。だから抽象的にならざるを得ない。マルクス・エンゲルスの「共産党宣言」(Communist Manifesto)もこのような感じであったはずです。
▼それにしても、この寄稿を読む限り、「小泉改革」を10年早く宣言してしまった、という感じがしないでもない。このような寄稿の場合、小沢さん自身がどの程度まで書くものなのか、私には分からないけれど、掲載前にしっかり見て自分の考えを反映したものかどうかをチェックしたはずですよね。そうだとすると、市場開放と自由貿易を信奉するThe Economistのような雑誌がいかに小沢さんに期待したかが分かりますね。
▼日本のメディアは、民主党の鳩山さんについて「小沢院政に陥るな」とか言っているけれど、私の 想像によると、外国の首脳たちは小沢さんの「第三の開国」は「日本の政治家の発言にしては分かりやすいじゃん?」と思っているのではないか・・・。 |
|
| 5)どうでも英和辞書 |
channel:代弁する
先ごろコンゴを訪問したヒラリー・クリントン米国務長官が、学生たちとの集会で質問をした学生に切れ気味の答えをして話題になりましたね。一人の学生がある問題について「ミスター・クリントンの意見をあなたの口から聞かせて欲しい」と質問したところ、ヒラリーは「鋭い口調で」次のように答えたのだそうです。
| Wait, you want me to tell you what my husband thinks? My husband is not
the secretary of state. I am. So, you ask my opinion, I will tell you my
opinion. I'm not going to be channeling my husband. |
| ちょっと待ちなさい。アナタは、私の夫が何を考えているのかを私に言わせたいわけ?私の夫は国務長官じゃない。私なのよ。だから、私の意見を聞いているのなら自分の意見を言いましょう。でも夫の意見を代理で述べる気はありませんからね。 |
ヒラリーのI'm not going to be channeling my husbandの中のchannelingという言葉が面白いと思ったのです。ルート、経路、排水路などの意味があるようですが、ヒラリーの使い方によると、他人に成り代わってそのひとの意見などを伝えるということですね。そんな意味もあるんですね。
それはともかく、この質問はフランス語で行われたものを通訳が英語に直したとのことで、質問しした学生は「ミスター・クリントン」ではなくて、「オバマ大統領」の意見を国務長官たるヒラリーの口を通して知りたいと言ったのだそうです。それがなぜか「ミスター・クリントン」になってしまった。ミスターの方は北朝鮮まで出かけて行って米人ジャーナリストを解放したりして国内ではヒーローになっているのに、自分は余り注目されないということで面白くないと思っていたヒラリーが、つい大人気もなく・・・というわけでヘンな話題になってしまった。ここをクリックすると、Wait, you want me to tell you...I'm not going to be channeling my husbandというヒラリーさんの怒りのコメントが肉声で聴けます。
patriots:愛国主義者
| Patriots always talk of dying for their country, and never of killing for their country. |
| 愛国主義者は「自分の国のために死ぬ」という話はするが「自分の国のために殺す」という話は絶対にしない。 |
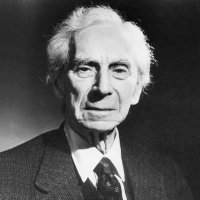 英国の哲学者・数学者、Bertrand Russellが"Has Man a Future?"(1962年発行)という本の中で言った言葉だそうです。ラッセル研究者と愛好家のためのポータルサイトによると、この本の日本語訳に寄せた序文の中でRussellは、広島・長崎への原爆投下について「あの原爆は戦争を終らせるために投下されたものではなかった。日本政府はそのまえに既に講和を申し出ていた。西洋諸国の政府はこのことを知っていた。原爆は無人地域で爆発させるようにという科学者たちの懇望が無視された」と書いているのだそうです。私自身は原文も日本語訳も読んだことがありませんが、愛国主義についてのこの言葉は当たっていますよね。「国」というのを「会社」(愛社精神)と置き換えても当たっている・・・。 英国の哲学者・数学者、Bertrand Russellが"Has Man a Future?"(1962年発行)という本の中で言った言葉だそうです。ラッセル研究者と愛好家のためのポータルサイトによると、この本の日本語訳に寄せた序文の中でRussellは、広島・長崎への原爆投下について「あの原爆は戦争を終らせるために投下されたものではなかった。日本政府はそのまえに既に講和を申し出ていた。西洋諸国の政府はこのことを知っていた。原爆は無人地域で爆発させるようにという科学者たちの懇望が無視された」と書いているのだそうです。私自身は原文も日本語訳も読んだことがありませんが、愛国主義についてのこの言葉は当たっていますよね。「国」というのを「会社」(愛社精神)と置き換えても当たっている・・・。
resilient:立ち直り能力
苦しいことを経験しても立ち直る能力に優れていることをresilientという。原状回復力という意味もある。話し言葉としてはあまり使われないけれど、新聞・雑誌などには頻繁に出てくる単語です。
米スタンフォード大学のDr Laura Carstensenが米国心理学会で発表した報告によると「ほとんどの人間は年をとるにつれてハッピーになる」(Most people get happier as they grow older)のだそうです。BBCのサイトに出ておりました。(例えば)若い者に比べると、年寄りは他人に悪く言われても精神的に立ち直るのが早いのだとか。more resilient to hearing personal criticismというわけですね。Carstensenが訴えたのは、高齢化することを否定的にばかりとらえるべきではない、ということだったのでありますが、そんなことはあえて心理学会で報告するようなことですかね。resilientは別の言い方をすると「厚かましくなる」ということですからね。
|
| 6)むささびの鳴き声 |
▼常識的な人間(私のこと)が常識的なアタマで極めて常識的なことを言わせてもらうと、昨日まで「XXさん」と呼ばれていた人が、ひとたび警察に逮捕されるや「XX容疑者」と呼ばれるのは、どう考えてもマトモではない。「容疑者」という言葉自体のおどろおどろしさもひどいけれど、新聞やテレビはどうしてこうも警察のやることなすことをそのまま受け容れてリンチのようなマネをするのか?XXという人を(それなりの理由や証拠があって)犯人ではないかと疑っているのは警察であって、メディアの人たちが証拠を握っているわけではない。
▼最近ある有名タレントが覚せい剤をやっていたというので「容疑者」としてテレビなどでさんざんな目に遭っています。報道の圧倒的多数が、この「容疑者」が麻薬をやることになった個人的な事情とか逃亡生活について根掘り葉掘り、しかも殆どが噂や「警察への取材」に基づいて伝えるものですね。いい加減にしてくれません?このタレントがいつからいつまで、どこにいたなどということは、私の生活にはなんの関係もない。ましてやこの人の「知られざる側面」など関係も関心もない。
▼それと「芸能界が麻薬に汚染されている」と深刻な顔してコメントするのも止めてくれません?その「芸能界」とマスメディアは相互に支えあっている関係にあるのだから、麻薬汚染を他人事みたいに言わないでほしいわけです。
▼というわけで、薬物所持で逮捕されてしまったタレントを「XX容疑者と呼ぶのは止めてXXさんと呼べ」と主張しようと思っていたら、逮捕された「容疑者」によるCDとかDVDが大いに売れているというニュースをテレビでやっておりました。つまりメディアが極悪人扱いしても、世間サマはそれほどでもないと考えているってこと?
▼と、極めて常識的なことを考えていたら、篠田博之というジャーナリストが「のりピー・押尾学ら芸能人の薬物逮捕事件に思う」というエッセイを書いているブログに行き当たりました。この人によると、いまの日本では薬物が浸透しているのに「薬物が具体的にどう怖いのか情報を流し、もし手を出した人が家族にいた場合どう対応するかなど、必要な情報がほとんど流されていない」のだそうです。そして新聞やテレビが、そのような議論をやらずに「単なる芸能スキャンダル」として消費しているのも「日本の特徴」であり「社会的教材」にはならないと言っています。実に納得のいく記事です。
▼今回もお付き合いをいただき有難うございました。暑い日が続きます。お身体に気をつけてお過ごしください。
|

←前の号 次の号→
messages to musasabi journal
|
![]()
何度か紹介したのですが、遅くとも来年(2010年)6月までには英国の総選挙が行われます。最近の英国の政治を見ると、1979年から1997年までの18年間が保守党、1997年から現在までの12年間が労働党という具合に一つの党の政権が長くもつという傾向にあるけれど、今の段階での世論調査によると次なる選挙ではキャメロン党首率いる野党の保守党がかなり優勢とされている。
が、新聞のネットを全て有料にする方針を発表。ネット版の有料化は、新聞にとって良いことだと思いますか?』というテーマで視聴者参加のディスカッションをやっていました。
英国の哲学者・数学者、Bertrand Russellが"Has Man a Future?"(1962年発行)という本の中で言った言葉だそうです。ラッセル研究者と愛好家のためのポータルサイトによると、この本の日本語訳に寄せた序文の中でRussellは、広島・長崎への原爆投下について「あの原爆は戦争を終らせるために投下されたものではなかった。日本政府はそのまえに既に講和を申し出ていた。西洋諸国の政府はこのことを知っていた。原爆は無人地域で爆発させるようにという科学者たちの懇望が無視された」と書いているのだそうです。私自身は原文も日本語訳も読んだことがありませんが、愛国主義についてのこの言葉は当たっていますよね。「国」というのを「会社」(愛社精神)と置き換えても当たっている・・・。